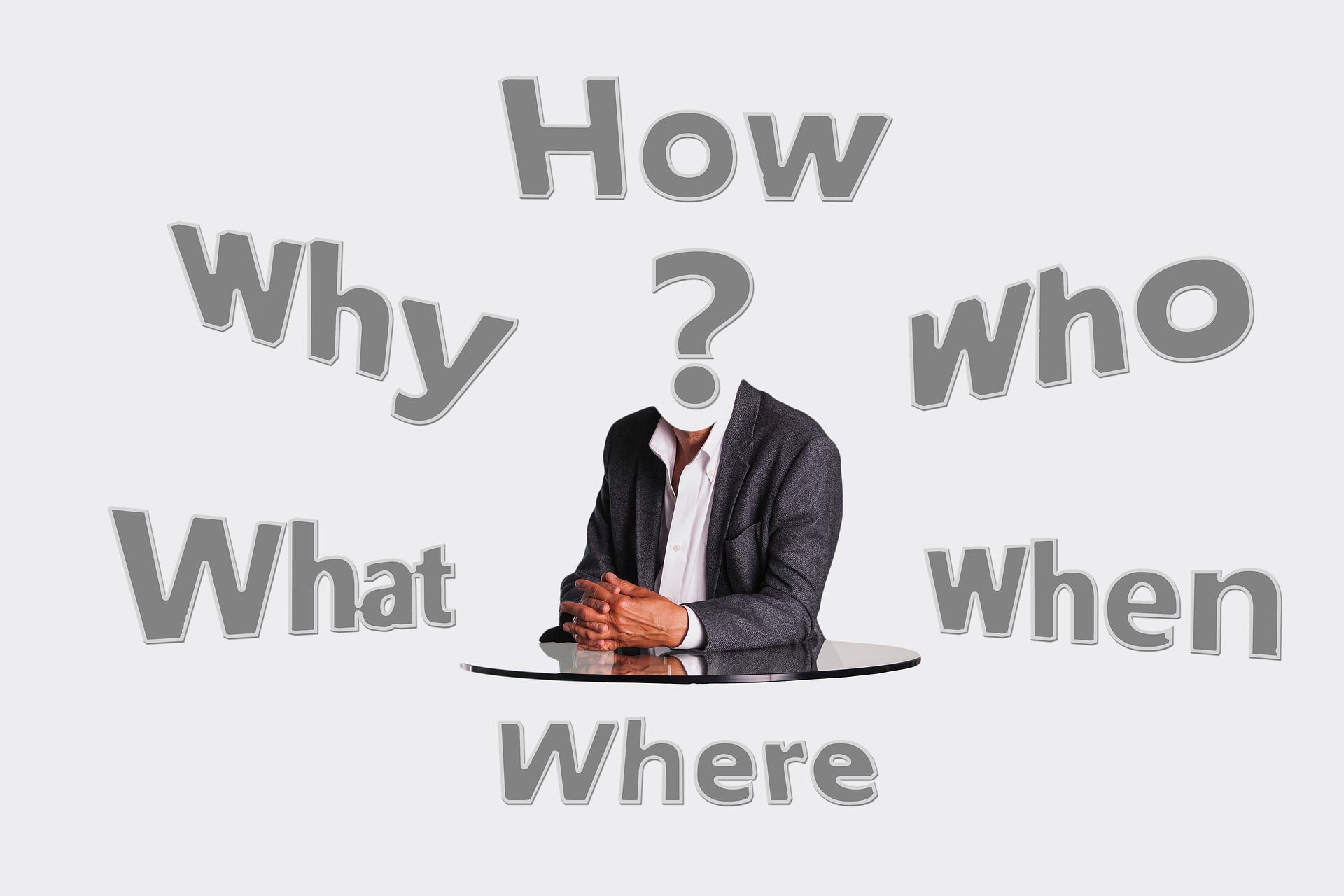当サイトのこのサイト立ち上げの「経緯」ページをご拝読いただいた方はなんとなくお察しいただいているかと思いますが、病院機能評価を新規受審で外部の補助なしに1発合格を勝ち取るのは至難の業と言わざるおえません。
そこで登場するのがコンサルティング(以下コンサル)です。
病院はコンサル企業と契約し、受審までの準備を支援してもらうことで新規受審でも様々な情報を得ながら効率的に準備を進めることができます。
コンサルって何してくれるの?
具体的にコンサルはどのようなことをしてくれるのかと言うと、コンサルティングを行う組織によって、またこちらの要望や予算額によっても内容に差が生じてきます。
新規のフルコンサルティングを行う想定で具体的にどのようなことを支援してくれるのか解説していきます。ざっくり箇条書きにすると以下のようなことを実施します。
- 病院機能評価に関する全体説明会の実施
- 病院機能評価受審準備のスケジューリングおよび課題管理
- 模擬審査(必要に応じて複数回実施)
- 項目担当者と改善のための打ち合わせ・質疑応答
- 病院機能評価の代表担当者の育成(必要に応じて)
基本的な訪問頻度は月に1回程度(病院の規模にもよります)で、上記のような内容をスケジュールに沿って実施します。
もちろん訪問日以外でも電話やメールなどで相談に乗ってくれます。
以下それぞれ解説していきます。
病院機能評価に関する全体説明会の実施
事前に病院機能評価の各項目の担当者を院内で決定していただき、その担当者全員に集まっていただきます。
そして病院機能評価とはどのようなものであるかや、各領域の概要、審査までの段取り、審査後も含めた病院機能評価の全体像について、また担当者のみなさんにはどのような役割を担っていただきたいかなどの説明を行います。
そこで質疑応答などの時間も設け、病院機能評価に対する心の準備をしていただきます。
病院機能評価受審準備のスケジューリングおよび課題管理
初回受審の場合、いくら院内にリーダーシップをはれる人材がいたとしても何の情報も知識もない状態で1から受審準備のスケジュールを院内で構築し、改善のPDCAサイクルを回すことは不可能に近いです。
そこで外部から客観的に病院の現状を把握し(後述する模擬審査などにて)、受審準備のスケジュールを立て、課題管理をしてくれるのがコンサルです。
模擬審査(必要に応じて複数回実施)
模擬審査は基本的には準備期間に2度実施します。
1回目はありのままの現状を調査し課題を洗い出すための、いわば現状分析としての模擬審査です。
ここで解説本の項目内容を満たしているかそうでないかをしっかり把握し、改善が必要な項目については課題管理表などにまとめます。
2回目は受審の1〜2ヶ月前に、最後の確認と本審査に慣れる目的で実施する模擬審査です。
もし初回の模擬審査で課題として挙げそびれてしまっていたものなどがあった場合は受審までに対応しなければならないため、本審査直前で実施することは避けましょう。
また、ケアプロセスと呼ばれる主要な病棟における患者の入院から退院までの医療行為を含む一連の流れを確認する審査に関しては、模擬審査以外でもできるだけ早い段階で複数回対応する練習をしておくことが望ましいです。
理由は、ケアプロセスに関しては電子カルテ上の記録に沿って説明を行う必要があり、その記録は日々の積み重ねによって作成されるもので一朝一夕に対応できるものではないからです。
また、審査員の指示で同意書などの書類の提出を求められた場合にどこに格納されているかなどが即座に対応できる必要があるため、PC操作に慣れておくという意味でも複数回練習しておくことが望ましいです。
項目担当者と改善のための打ち合わせ・質疑応答
ここがコンサルのメイン業務とも言える内容です。
フルコンサルティングの契約をおこなった場合、毎月コンサルタントが病院に訪問し、課題の進捗状況などを各項目の担当者と確認します。
改善方針で詰まっている場合は他院の事例や具体的な合格指標となる数値などの情報をコンサルからたくさん聞いて取り入れましょう。
多くの病院の事例を見てきているコンサルはそれだけ病院機能評価に合格するためのコツを知っています。課題をどのように改善すれば合格基準を満たすことができるかわかっています。
コンサルをもし契約しているのであればコンサルが持っている情報を最大限引き出して活用させてもらいましょう。
ただし、病院によって状況は異なるため他院の事例がそのまま適応できる場合とそうでない場合があるのも事実です。そんな時こそコンサルの腕の見せ所とも言えます。
各種項目の内容の背景にはそれ相応の目的があります。その目的が達成できるのであれば手段は病院の状況に合った手段を用いればいいのです。その仕組みづくりをすることこそがコンサルの手腕が発揮されるところです。
項目の担当者は現状をしっかりと把握し、コンサルに伝え、実現可能な施策をコンサルと導き出しましょう。
病院機能評価の代表担当者の育成(必要に応じて)
2回目以降の受審ではコンサルに頼らずに合格を勝ち取りたいと考える病院も多いと思います。
そのような場合はコンサルの代わりになるような人材がもちろん必要となります。具体的にはこれまでに記載してきたような内容(審査準備のスケジューリング、課題管理、模擬審査、項目担当者との打ち合わせ など)ができる人材です。
コンサルとの契約は人材育成まで含まれないことがほとんどです。
しかし契約するコンサルの組織によっては別途料金を上乗せして対応してくれるところもあるでしょう。
もしくはコンサルの訪問時には終始コンサルにつきっきりで思考法などを見て覚える担当者を置くのもありです。
意識の高い病院は後者の方法で次期担当者を育成されているところも実際にあります。
この役割を進んで担いたいと思う方は少ないかもしれませんが、確実に病院の中である種のプロフェッショナルとなることができ、一目置かれる存在となるでしょう。
やりがいは計り知れないです。